パイマッチの考え方
1998年11月3日掲載
調整の仕方はわかっているとしても、いざ作るとなるともう一つ釈然としないのがパイマッチです。ここでは基本的な動作と調整の仕方、それに作り方について考えてみました。
少しつっこんだ内容になっています。
動作と設計
パイマッチの基本的な考え方は比較的簡単です。C+LのL型回路とL+CのL型回路が従属されているとして扱うと楽です。最初のL型回路でR1があるインピーダンスR2まで下げられ、2番目のL型回路でそれがR3、例えば50Ωまであげられるというものです。
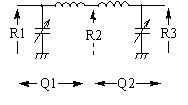
バリコンの容量は、後述しますが、おのおののL型回路のインピーダンス変換比を決定するQ値をパラメータとして、簡単に求められます。つまり、
Xc=R/Q
ここにRは、R1とR3です。この関係は、前後いずれのL型回路についても共通に成り立ちます。
それで、R3は50Ωでよいわけですが、R1や、Q1やQ2をどう選ぶか、これが問題です。
これらが決まれば、Xc、つまり、2つのバリコンの容量は上の式から求められます。そして、Cが決まれば自動的にLも決まります。
これがつまり、設計手順です。設計手順と言うより、計算手順かもしれませんね。。。
Rの決め方
Rの決め方には2通りの方法があります。
基本的には後者がおすすめですが、自由に使いこなすには特性曲線を実験などで求める必要があり、少し面倒です。
(1)R=(終段真空管のプレート電圧)/(プレート電流のk倍)で求める方法
ここでkは、増幅する信号と終段動作によって変わってきます。信号が連続キャリヤで、終段がA級動作する場合は1.3程度、B級では1.6程度、C級では2程度とします。
SSBのような波高値の高い信号の時はもう少し高めに設定し、一般的なAB級では1.8程度にします。SSBをA級で増幅する場合はどうするのでしょうか? 私にはわかりません。
このようにkの値でプレート負荷抵抗を求める理由は、動作クラスによって、プレート電流の流れ方が違うということに起因します。A級では基本波(電波)の1サイクル期間すべてにわたって電流が流れますが、AB級やB級では半周期ほどしか流れず、さらにC級では電流は90度以下しか流れないといったことも起きます。
そうすると、たとえメーター指示値が同じであったとしても、たとえばC級のようにパルス状に流れる電流と、A級のように連続的に流れる電流では、波高値は全く違うと予想されます。このあたりを補正して、最大出力が得られる負荷抵抗を正しく予想しようというのがk値の導入の目的であると思われます。
(2)終段管の静特性曲線を利用する方法
一般のオーディオアンプのように、負荷直線として結んだプレート供給電圧とEc=0の肩電圧を利用して
負荷抵抗を求める方法です。詳細は適当な解説書に譲るとして、式だけ抜き出しますと、
R=(プレート供給電圧-Ec=0の肩電圧)/(Ec=0の肩電流)×2
試しに6146を例に、プレート電圧600V、スクリーン電圧200Vの場合について計算してみますと、
プレート特性の図より、Ec=0の肩電圧、肩電流はそれぞれ、60V、350mA程度ですから、
R=(600-60)/0.35×2=3086Ω
となり、規格表にある3Kという値と良好に一致します。
これ以上進めるには、AB球の動作バイアス点をどこに選ぶかなど、少々面倒な検討も必要になります。。。
Qの決め方
1番目のL型回路のQ1、2番目のL型回路のQ2決めれば2つのバリコンの容量が求まりますが、パイマッチ
回路では、最初のL型回路のQ1を決めれば2つ目のQ2は自動的に決まります。
なぜそうなるか? L型回路の動作を考えればすぐにわかります。
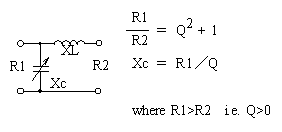 上図を見てください。最初のL型回路の入力と出力のR1とR2の比は、
上図を見てください。最初のL型回路の入力と出力のR1とR2の比は、
R1/R2=Q1^2+1
たとえば、R1=4K、Q1=12とすると、R2は
R2=R1/(Q1^2+1)=27.6Ω
ここで、負荷は50Ωなどに決まっていますから、2つ目のL型回路によるR2=27.6からR3=50Ωへの変換は、
Q2=(50/27.6-1)^0.5 = 0.9
と自動的に決まるわけです。
値の善し悪しは別にして、Q1=12と決めると、4Kから50Ωへのインピーダンス整合は、この条件以外では
あり得ません。
さて、Q1は、一般に12程度にとります。リニヤアンプでは15程度にする場合もあるようです。一般に、10から15の範囲であれば問題ないといわれているようです。
この値の根拠、あるいは本当によいのかどうかは私にはわかりませんが、大きくすると、同調回路としてのシャープさは出ますが、それは環流電流の増加を意味し、結局熱による損失の増大を招き、一方小さすぎると、高調波に対する防備が手薄になって、ちょうど10から15位が手頃であると解説されている場合が多いようです。
試しに、Qをパラメータに、第2高調波と第5高調波に対して、基本波に比較して同調電流が何dB低下するか、定義式から簡単に計算してみました。
| Q | 5th | 2nd |
|---|
| 5 | -34.0 | -26.0 |
| 8 | -38.0 | -30.1 |
| 10 | -40.0 | -32.0 |
| 15 | -43.5 | -35.6 |
| 20 | -46.0 | -38.0 |
Qが10から15の範囲では、第2高調波に対しては十分な減衰とはいえないようです。また、Qが少々変化しても、高調波抑圧という観点からはあまり大きな変化はないように思えます。
以上述べたQの決定について再度まとめます。値の善し悪しは別にして、Q1を10~15程度に決めると、R1とR2の関係が決まり、あとはR2とR3の関係から自動的にQ2が決まります。
以上で、R1とQが決まりました。それにより、直ちにバリコンのXcを求めることができます。つまり、
Xc1=R1/Q1、 Xc2=R3/Q2
Xcは、ω=2πfで容量に直せます。さらに、2つのバリコンの合成容量で目的の周波数に共振するLを求めれば万事OKです。
計算の順序を整理すると、
1)R1とQ1を決める。
2)プレートバリコンを算出
3)Q2を計算して、ロードバリコンを算出
4)Lを計算
ここで、ひとつ興味あることに気づきます。R1とQ1が決まればR2が決まりますが、そこでQ2は負にはできませんから、常にR2<R3でないとパイマッチは使用できないということです。
逆に、R3を50Ωと決めると、R2<50ΩとできるようなQ1は、R1に対して決まってしまい、それがQ1の推奨範囲を超えていたらパイマッチは使えないわけです。
QRPの送信機で、極端に電流が少なく、プレート負荷が高くなるよな場合、あるいは本格的な送信管を高圧低電流で使用するような場合には、Q1は極端に大きくなってパイマッチは使えません。このような場合はリンクコイルでマッチングをとる方法が使えます。また別項で説明します。
パイマッチの定数
ここまでのまとめとして、各負荷インピーダンスに対する、R2=50、75Ω、Q=12,15としたときの回路素子定数を求めておきました。
| R1 | R3 | Q | Xc1 | XL | Xc2 | |
R1 | R3 | Q | Xc1 | XL | Xc2 |
|---|
1000 | 50 | 12 | 83.33 | 100 | 20 | 1000 | 75 | 12 | 83.33 | 104.43 | 23.86 |
| 2000 | 50 | 12 | 166.66 | 187.86 | 30.86 | 2000 | 75 | 12 | 166.66 | 194.57 | 35.60 |
|---|
| 3000 | 50 | 12 | 250 | 272.90 | 42.00 | 3000 | 75 | 12 | 250 | 281.79 | 46.29 |
|---|
| 4000 | 50 | 12 | 333.33 | 355.90 | 55.47 | 4000 | 75 | 12 | 333.33 | 367.20 | 57.20 |
|---|
| 5000 | 50 | 12 | 416.66 | 436.92 | 74.53 | 5000 | 75 | 12 | 416.66 | 451.17 | 69.18 |
|---|
| 6000 | 50 | 12 | 500 | 515.43 | 109.54 | 6000 | 75 | 12 | 500 | 533.85 | 83.20 |
|---|
| 7000 | 50 | 12 | 583.33 | 588.43 | 264.57 | 7000 | 75 | 12 | 583.33 | 615.22 | 100.80 |
|---|
| 8000 | 50 | 12 | 666.66 | #NUM! | #NUM! | 8000 | 75 | 12 | 666.66 | 695.14 | 125.10 |
|---|
| 9000 | 50 | 12 | 750 | #NUM! | #NUM! | 9000 | 75 | 12 | 750 | 773.15 | 164.31 |
|---|
| 10000 | 50 | 12 | 833.33 | #NUM! | #NUM! | 10000 | 75 | 12 | 833.33 | 847.98 | 253.54 |
|---|
| 11000 | 50 | 12 | 916.66 | #NUM! | #NUM! | 11000 | 75 | 12 | 916.66 | #NUM! | #NUM! |
|---|
| 12000 | 50 | 12 | 1000 | #NUM! | #NUM! | 12000 | 75 | 12 | 1000 | #NUM! | #NUM! |
|---|
| 13000 | 50 | 12 | 1083.33 | #NUM! | #NUM! | 13000 | 75 | 12 | 1083.33 | #NUM! | #NUM! |
|---|
| 14000 | 50 | 12 | 1166.66 | #NUM! | #NUM! | 14000 | 75 | 12 | 1166.66 | #NUM! | #NUM! |
|---|
| 15000 | 50 | 12 | 1250 | #NUM! | #NUM! | 15000 | 75 | 12 | 1250 | #NUM! | #NUM! |
|---|
| |
|---|
| 1000 | 50 | 15 | 66.66 | 80.57 | 15.57 | 1000 | 75 | 15 | 66.66 | 84.04 | 18.77 |
| 2000 | 50 | 15 | 133.33 | 151.82 | 23.18 | 2000 | 75 | 15 | 133.33 | 156.93 | 27.43 |
| 3000 | 50 | 15 | 200 | 221.19 | 30.06 | 3000 | 75 | 15 | 200 | 227.73 | 34.78 |
| 4000 | 50 | 15 | 266.66 | 289.39 | 37.01 | 4000 | 75 | 15 | 266.66 | 297.33 | 41.68 |
| 5000 | 50 | 15 | 333.33 | 356.69 | 44.54 | 5000 | 75 | 15 | 333.33 | 366.06 | 48.51 |
| 6000 | 50 | 15 | 400 | 423.18 | 53.19 | 6000 | 75 | 15 | 400 | 434.09 | 55.51 |
| 7000 | 50 | 15 | 466.66 | 488.87 | 63.79 | 7000 | 75 | 15 | 466.66 | 501.52 | 62.90 |
| 8000 | 50 | 15 | 533.33 | 553.70 | 77.84 | 8000 | 75 | 15 | 533.33 | 568.41 | 70.90 |
| 9000 | 50 | 15 | 600 | 617.47 | 98.90 | 9000 | 75 | 15 | 600 | 634.77 | 79.79 |
| 10000 | 50 | 15 | 666.66 | 679.67 | 138.67 | 10000 | 75 | 15 | 666.66 | 700.60 | 89.96 |
| 11000 | 50 | 15 | 733.33 | 738.12 | 302.76 | 11000 | 75 | 15 | 733.33 | 765.88 | 101.97 |
| 12000 | 50 | 15 | 800 | #NUM! | #NUM! | 12000 | 75 | 15 | 800 | 830.56 | 116.77 |
| 13000 | 50 | 15 | 866.66 | #NUM! | #NUM! | 13000 | 75 | 15 | 866.66 | 894.53 | 136.06 |
| 14000 | 50 | 15 | 933.33 | #NUM! | #NUM! | 14000 | 75 | 15 | 933.33 | 957.63 | 163.38 |
| 15000 | 50 | 15 | 1000 | #NUM! | #NUM! | 15000 | 75 | 15 | 1000 | 1019.50 | 208.01 |
上表の、値が入っていないところは、上に述べたような理由によりパイマッチが原理的に成り立たない範囲です。
実際の使用に当たっては、アンテナが純抵抗であるとは限りませんから、この「成り立たない範囲」周辺での使用を想定した設計はさけた方が良さそうです。
以上、通り一辺の説明をしました。これらは、適当な関連書籍をくればどこかに載っている内容だと思います。
なお書籍によっては、パイマッチ回路をL型回路2つに分けて上記の流れで考えるものや、ひとつのLCネットワークとして考えてしまうものがあります。後者では、Qはひとつしか出てきませんが、上述のQ1に相当すると思えば問題ありません。Q2は、自動的に決まるという考えで消去して扱っているからです。
パイマッチによるインピーダンスマッチング
さて、ここではつぎに、パイマッチについてよく言われる特徴:
広い範囲にインピーダンスマッチングが可能 ということについて考えてみます。
まず、インピーダンスマッチングが可能という意味ですが、これは、値の固定したコイルを用いて、2つのバリコンを調整すれば、幅広いインピーダンスにマッチングができる、そのように操作できるという意味です。
たとえば、上の表で求めた、R3=50Ω負荷に適合したコイルを用いて、75Ωに整合させた場合のC値と回路Q(Q1)を求めてみると、次表のようになります。
| R1 | R3 | XL | Xc1 | Xc2 | Q |
|---|
| 1000 | 75 | 100 | 79.68 | 22.72 | 12.55 |
| 2000 | 75 | 187.86 | 160.64 | 34.05 | 12.45 |
| 3000 | 75 | 272.90 | 241.35 | 44.13 | 12.43 |
| 4000 | 75 | 355.90 | 322.32 | 54.31 | 12.41 |
| 5000 | 75 | 436.92 | 401.92 | 64.87 | 12.44 |
| 6000 | 75 | 515.43 | 481.15 | 76.69 | 12.47 |
| 7000 | 75 | 588.43 | 555.11 | 88.73 | 12.61 |
| 8000 | 75 | #REF! | #REF! | #REF! |
| 9000 | 75 | #REF! | #REF! | #REF! |
| 10000 | 75 | #REF! | #REF! | #REF! |
| 11000 | 75 | #REF! | #REF! | #NUM! |
| 12000 | 75 | #REF! | #REF! | #NUM! |
| 13000 | 75 | #REF! | #REF! | #NUM! |
| 14000 | 75 | #REF! | #REF! | #NUM! |
| 15000 | 75 | #REF! | #REF! | #NUM! |
|
|---|
| 1000 | 75 | 80.57 | 64.102 | 18.017 | 15.6 |
| 2000 | 75 | 151.82 | 128.86 | 26.40 | 15.52 |
| 3000 | 75 | 221.19 | 194. | 33.54 | 15.46 |
| 4000 | 75 | 289.39 | 259.23 | 40.18 | 15.43 |
| 5000 | 75 | 356.69 | 324.46 | 46.71 | 15.41 |
| 6000 | 75 | 423.18 | 389.35 | 6 53.28 | 15.41 |
| 7000 | 75 | 488.87 | 454.25 | 60.14 | 15.41 |
| 8000 | 75 | 553.70 | 518.47 | 67.31 | 15.43 |
| 9000 | 75 | 617.47 | 582.52 | 75.09 | 15.45 |
| 1000 | 0 75 | 679.67 | 645.16 | 83.36 | 15.5 |
| 11000 | 75 | 738.12 | 705.58 | 92.04 | 15.59 |
| 12000 | 75 | #REF! | #REF! | #REF! |
| 13000 | 75 | #REF! | #REF! | #REF! |
| 14000 | 75 | #REF! | #REF! | #REF! |
| 15000 | 75 | #REF! | #REF! | #REF! |
もともとは、いずれもQ=12、15で50Ω負荷に対して設計してしていたものですが、このようにR3として75Ω負荷をつなぐとCの値が変化し、同調回路としてのQも変化しますが、インピーダンスマッチングはとれます。
つまり、パイマッチで幅広いインピーダンスにマッチングできるというのは、コイルをさわらなくとも、2つのCを操作するだけで、回路Qが変動してインピーダンスマッチングがとれるという意味だということがわかります。
この場合、Qは設計値からは大きく変化せず、ほとんど誤差の範囲だろうと思われます。
試しにもう少し範囲を広げてみましょう。
R1を4Kとし、R3=40Ω~110Ωのインピーダンス変換について、XL=350Ωとしたとき、回路Qがどのような値になるか、バリコンはどのような値になるかを求めてみました。XL=350Ωというのは、R1=4K、R3=50Ωに、Q=12.2程度で整合する条件です。
| R1 | R3 | Q | Xc1 | XL | Xc2 |
|---|
| 4000 | 40 | 11.98 | 333.86 | 350.02 | 59.93 |
| 4000 | 45 | 12.11 | 330.22 | 350.01 | 55.31 |
| 4000 | 50 | 12.22 | 327.25 | 350.02 | 53.29 |
| 4000 | 55 | 12.32 | 324.67 | 350.02 | 52.42 |
| 4000 | 60 | 12.40 | 322.39 | 350.02 | 52.14 |
| 4000 | 65 | 12.48 | 320.33 | 350.02 | 52.20 |
| 4000 | 70 | 12.56 | 318.42 | 350.01 | 52.48 |
| 4000 | 75 | 12.63 | 316.65 | 350.00 | 52.89 |
| 4000 | 80 | 12.69 | 315.01 | 350.00 | 53.39 |
| 4000 | 85 | 12.76 | 313.47 | 350.02 | 53.96 |
| 4000 | 90 | 12.82 | 312.01 | 350.02 | 54.56 |
| 4000 | 95 | 12.87 | 310.60 | 350.01 | 55.19 |
| 4000 | 100 | 12.93 | 309.28 | 350.01 | 55.84 |
| 4000 | 105 | 12.98 | 308.02 | 350.02 | 56.50 |
| 4000 | 110 | 13.03 | 306.79 | 350.01 | 57.16 |
これより、R1一定の時、コイル一定ならば、R3が高くなるほど回路Qも上昇することがわかります。このことから、たとえばR3=50Ωから75Ωの負荷に対してQ=12で動作させようとすると、R3=62Ωほどに対してQ=12で動作するコイルを求め、それを作れば、50Ωの時には若干低め、75Ωの時には若干高めのQとなって、それぞれマッチングがとれるだろうということがわかります。
しかし、先に述べたとおり、Qはどの程度の値がよいのか、それ自体が問題です。
L一定でも、上表のようにかなり広い範囲にマッチングがとれますから、Qにはあまりこだわらずに、単純に12とか13とかにおいてみて、適当なLを巻いて動作させるというスタンスが実際的だと思います。
最大出力が得られる負荷条件とパイマッチ
下でも述べますが、実際の運用場面でのパイマッチの調整は、出力パワーをパラメータにそれが最大になるように調整するといった簡単なものです。そして、最大出力が得られるときに、都合よくインピーダンスマッチングができたと考えるわけです(逆に言えばその時、パイマッチ回路によって、終段管がもっとも効率よく働く負荷抵抗が与えられたということです)。
パイマッチの設計時には、上で述べたように、あらかじめその状態:最大出力が得られる状態 のとき、終段管がどのような負荷抵抗で動作しているか予測して、その予測負荷抵抗のもとに、ある定めたQ値で、もっとも効率よくインピーダンス変換ができるように回路定数を決めるというような設計手法をとりました。
ここで、負荷抵抗R1は先に述べたKを基準に求めますが、この値自体が実はよくわかりません。おそらく長い積み上げのもとに決められた数値だとは思いますが、アマチュア的な検証の方法もありません。つまり、最大出力が得られるときのR1が、パイマッチ設計で想定した値とどのくらいずれているのか、まったくわからないわけです。パイマッチも、一応それなりの思想を持った設計はしているが、動作の検証はしていない、つまり、やみくもに動いている状態に近いといえます。
そこで、R1が設計値からずれていたとして、それがどの程度、決定した動作Qに影響を与えるか調べてみました。ここでは、R1=3K、5Kとして、設計中心値4Kに対し、2,3割の誤差を含んだ場合を想定して上述と同様の計算を行ってみました。
| R1 | R3 | Q | Xc1 | XL | Xc2 | | R1 | R3 | Q | Xc1 | XL | Xc2 |
|---|
| 3000 | 40 | 8.69 | 345.22 | 346.28 | 281.33 | 5000 | 40 | 15.05 | 332.22 | 350.66 | 44.17 |
| 3000 | 45 | 8.87 | 338.21 | 350.60 | 101.86 | 5000 | 45 | 15.2 | 328.94 | 350.00 | 43.13 |
| 3000 | 50 | 9.02 | 332.59 | 350.79 | 81.90 | 5000 | 50 | 15.3 | 326.79 | 350.12 | 43.01 |
| 3000 | 55 | 9.15 | 327.86 | 350.33 | 73.94 | 5000 | 55 | 15.4 | 324.67 | 350.03 | 43.21 |
| 3000 | 60 | 9.25 | 324.32 | 350.21 | 70.16 | 5000 | 60 | 15.48 | 322.89 | 350.09 | 43.65 |
| 3000 | 65 | 9.34 | 321.19 | 350.02 | 68.07 | 5000 | 65 | 15.55 | 321.54 | 350.45 | 44.26 |
| 3000 | 70 | 9.41 | 318.80 | 350.21 | 67.06 | 5000 | 70 | 15.64 | 319.69 | 350.18 | 44.82 |
| 3000 | 75 | 9.47 | 316.78 | 350.53 | 66.62 | 5000 | 75 | 15.7 | 318.47 | 350.45 | 45.53 |
| 3000 | 80 | 9.53 | 314.79 | 350.69 | 66.46 | 5000 | 80 | 15.79 | 316.65 | 350.01 | 46.14 |
| 3000 | 85 | 9.61 | 312.17 | 350.04 | 66.27 | 5000 | 85 | 15.85 | 315.35 | 350.04 | 46.85 |
| 3000 | 90 | 9.66 | 310.55 | 350.28 | 66.53 | 5000 | 90 | 15.9 | 314.46 | 350.44 | 47.64 |
| 3000 | 95 | 9.72 | 308.64 | 350.10 | 66.78 | 5000 | 95 | 15.95 | 313.47 | 350.67 | 48.39 |
| 3000 | 100 | 9.77 | 307.06 | 350.17 | 67.18 | 5000 | 100 | 16 | 312.5 | 350.86 | 49.14 |
| 3000 | 105 | 9.82 | 305.43 | 350.09 | 67.61 | 5000 | 105 | 16.08 | 310.94 | 350.38 | 49.76 |
| 3000 | 110 | 9.87 | 303.95 | 350.096 | 68.10 | 5000 | 110 | 16.15 | 309.59 | 350.08 | 50.41 |
上のように、傾向としては、計算で求めた負荷抵抗より、実際の動作抵抗が高ければQは高くなり、抵抗が低ければQも低下するということがわかります。
結論として、実は最大出力が得られるR1が計算で求めた値とずれていたとしても(この例では、4K、Q=12程度として計算したコイルを用いて3K又は5Kにずれるとしました)、設計Q=12に対しQ=9から16程度の変化で、驚くほど大きく設計値からQがずれるというものでもなく、おおむね設計したオーダーで調整ができることがわかりました。
Qは、10から15の範囲であれば大丈夫などといわれていますから、かなり大雑把な話ではありますが、この程度の抵抗の見込み違いは、実際にはあまり問題にはならないのだろうと思われます。
パイマッチの調整
以上の検討は、次のような実際の運用場面でどうファイナルを調整すべきかといった問題に一定の方針を示してくれます。
たとえば、マイクゲインを絞ってローカルQSOをするときのファイナルの調整はどうあるべきか。。。 最大パワーで調整して、単にマイクゲインを絞れば、ファイナルの負荷抵抗R1は高めになり、その結果上の検討から動作Qは上昇しますから、ローパワーQSOにはうってつけの、きれいな電波になるでしょう。逆に、パワーを十分入れない状態で調整したファイナルに、その調整時以上のパワーを入れて使うと、、、Qが低下して、インターフェアレンスを引き起こす可能性も出ます。危険です。
あるいは、プロセッサーを入れて、トークパワーを上げて、など、ガンガンやることを想定する時には、ファイナルの動作自体も低めのR1でということになるでしょうから、そういう状態でもうまく整合がとれるよう、たとえばXC2を大きめにする(ロードバリコンを抜きぎみにする)などの配慮が必要だと思います。しかしその場合でも、設計した標準値以下のR1でファイナルが動作する場合には、上述のように想定した値よりもQが低下する可能性があることを頭の隅においておくべきです。
なお、このような使い方をする場合、先に述べたKの値も変化するでしょうからどのような負荷抵抗になるのか推定できず、Lの値自体をあらかじめどちらかに寄せる方が無難かもしれません。これについては後述します。
また、昔の八重洲のFT101やFT401など、キットによって10W機が簡単に100Wに増力できるというような場合、あるいは、そういった将来のQROを想定して考える場合、一般にQROした後の方が終段管の負荷抵抗R1が低下するでしょうから、そういったことを考えるなら、あらかじめ負荷抵抗R1の低下を見込んだLを考えておく必要があります。たとえばFT401では、10W動作の時は300V、100mA程度、100W動作の時は600V、300mA程度ですから、後者の方がインピーダンスがいくらか低下しているだろうと想像できます。コイルのタップを変化させることなくこの両者に対応させようと、たとえば100W動作の時に適切なQで動作するようにLを設計したとすると、10W動作の時には、Qはかなり高くなっていただろうと思われます。
そういう設定になっていて初めて、100W動作の時に想定するQが得られるわけで、逆にこういう配慮がなされていなかったとすると、100Wに増力したとき、パワーアップとQの低下がいずれも悪い方に作用して、TVIなどが出やすくなる結果につながると思われます。
といっても、先に計算したQの値と高調波の抑圧効果によると、たとえば12と決めたQが実際の動作で10だったとしても、それほど大きな変化はないようではあります。もっとも、テレビ球は詳細な動作曲線の持ち合わせが無く、負荷特性がどうなっているか、きっちりした検討が
できているわけではありません。。
コイルの巻き方
話が長くなりましたが、それではそういうLは、大きめにするのがよいのか、あるいは小さめにするのがよいのか、あるいは、計算で求めたものをばっちり作るのは難しいとするなら(必然的に誤差が出るとするなら)、その誤差はどちらの方向に出せばよいか、などという観点からLについて考えてみます。下の表では、4K対50Ωで、Qをいろいろに変化させた場合の定数を求めてみました。
| R1 | R3 | Q | Xc1 | XL | Xc2 |
|---|
| 4000 | 50 | 10 | 400 | 416.33 | 97.59 |
| 4000 | 50 | 10.2 | 392.15 | 409.72 | 89.37 |
| 4000 | 50 | 10.4 | 384.61 | 403.21 | 82.81 |
| 4000 | 50 | 10.6 | 377.35 | 396.81 | 77.42 |
| 4000 | 50 | 10.8 | 370.37 | 390.54 | 72.89 |
| 4000 | 50 | 11 | 363.63 | 384.41 | 69.00 |
| 4000 | 50 | 11.2 | 357.14 | 378.42 | 65.62 |
| 4000 | 50 | 11.4 | 350.87 | 372.57 | 62.64 |
| 4000 | 50 | 11.6 | 344.82 | 366.87 | 59.99 |
| 4000 | 50 | 11.8 | 338.98 | 361.31 | 57.61 |
| 4000 | 50 | 12 | 333.33 | 355.90 | 55.47 |
| 4000 | 50 | 12.2 | 327.86 | 350.62 | 53.51 |
| 4000 | 50 | 12.4 | 322.58 | 345.48 | 51.72 |
| 4000 | 50 | 12.6 | 317.46 | 340.47 | 50.07 |
| 4000 | 50 | 12.8 | 312.5 | 335.59 | 48.55 |
たとえばLが誤差を持ち、実現されたLが設計値より大きくなったとすると、傾向としては、Qが低めになることがわかります。逆に、Lが小さくなればQが上昇します。
先に述べたように、計算で求めた負荷抵抗より実際の動作抵抗が高ければQは高くなり、抵抗が低ければQも低下するということがわかっていますから、このことと組み合わせてみると、Lをどのように作るべきかの方針が得られます。
・R1が低めに出そうなら、Lをあらかじめ小さめにする。それで、Qの計算値からの低下は防止できる。
・R1が高めに出そうなら、Lをあらかじめ大きめにしておく。それでQの無用な上昇を防げる。
前者の、R1が低めに出るということは、入力パワーが大きめになるということと同義ですから、先に述べたプロセッサーを入れるとかQROする等を想定する場合など、Lは小さめになるように心がけ、大きめに誤差を出すということがないよう注意した方が無難です。反対にLが大きめになったりすると、Qが設計目標値より低下して、思わぬTVIの発生などにつながる可能性もあります。ただでさえ、プロセッサー処理やQROできたない(お世辞にもきれいとはいえない)電波になっているはずですから。
また後者はヒソヒソQSO等でしょうが、これ専用に機械を作るということはあまりないと思われます。
まとめ
以上、いろいろみてきました。まず、一通りの設計について説明し、データを示しました。次に広いインピーダンスにマッチング可能という意味合いを調べました。RもQも、あまりこだわる必要はなく、適当な目安の元に値を定めてLを決め、それを用いて最大出力が得られるように調整しさえすれば、Rが実際には設計値からずれていたとしても、適当なQで幅広くインピーダンスマッチングができることがわかりました。
具体的にR1のプラマイ3割程度の変化に対して、Qの変化は比較的ブロードで、Q=12で設計した場合には、R1が少々変わっても(実際の最適動作条件が設計条件と変わったとしても)Q=10から15の範囲におおむね入るだろうことがわかりました。
実際の動作については、負荷R自体も推定値であり、たとえば最大出力が得られるときに(そのようなインピーダンスマッチングになっているときに)どのような負荷、回路Qで動作しているのか、設計値に対して実際にどう動いているのか、はっきりとした推定(測定)は難しいと思われ、実際どう動いているか検証のしようがないといった制約上、パイマッチの設計(バリコンは調整できますから、特にコイルの設計)は、RやQをある方針に従って決めたときにこう動くだろうという一つの目安であるととらえるくらいが適当なのだろうということについて述べました。また、全体として、Lは小さめを心がける限り、ある程度ラフに考えても実用的な問題は少ないと思われることについて述べました。
自作のページへ